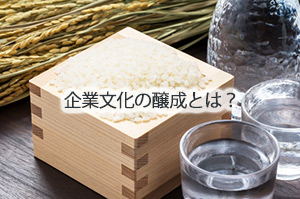
醸成とは、醸造でお酒が出来上がることです。少しずつ発酵が進んでいって、お酒が出来上がります。
美味しいお酒をつくるためには、美味しい原材料が必要です。そして、発酵環境を維持しながら発酵の具合を確認し、美味しいお酒になります。
企業文化が定着することは、醸成と似ているところがあります。
企業文化とは、その企業の考え方や行動のことです。挨拶の仕方、クレームやトラブルの対応など、企業によって考え方ややり方が異なりますが、それが企業文化の違いとも言えます。
企業はすべからく何等かの企業文化があります。企業文化の良し悪しで、会社の規模が決まるようなところがあります。悪い企業文化があれば、会社は大きくなりませんので、会社を大きくしたければ、新しく企業文化を醸成させて、立派な会社を目指さなければいけません。
この記事では、小企業の社長向けに、企業文化の醸成について述べたいと思います。
企業文化の醸成とは?
企業文化の醸成とは、要するに、仕事の考え方ややり方を社員全員に浸透させ、定着させることです。企業文化が醸成した状態とは、そのような企業文化が定着した状態のことです。
社員は仕事で何らかのことを基準に行動をしますがが、その行動が社長の意図する基準になっている状態になっていることです。
人を育てることは、とても手間暇がかかります。時にはムダのように思えるような教育をしますが、教育した内容を社員が忘れてしまうとしても、それを続けていかなければいけません。
社員それぞれが、バラバラの基準で仕事をしているのであれば、それはある意味で、仕事が属人化した状態ですし、烏合の衆とも言え、組織経営ができていない状態とも言えます。
立派な会社は、社員全員が連携し、標準的な企業よりも高いレベルで仕事ができている企業です。
一部の優秀な社員は、高い基準で仕事ができていることでしょう。しかし、その一人の優秀な社員一人だけですと、戦況が改善されることはありません。宮本武蔵は剣術で優れた才がありましたが、関ヶ原の戦いでは、一兵卒に過ぎません。宮本武蔵は、西側陣営に与していたとされますが、彼一人では戦況を覆すことができません。
企業文化が醸成された状態は、社員が組織戦で戦い、誰もが一定以上の成果を出せるようになっている状態です。
このことは、会社が中企業やそれ以上に成長していくためには、登竜門となっています。
企業文化の基準となる業務マニュアル
企業文化醸成のスタートは経営理念づくり
企業文化を醸成するための基となるものは、社長が決める基準ですが、その最上位のものが経営理念です。経営理念は、会社での最上位のマニュアルとも言えます。
経営理念は作成するだけでなく、浸透させることが大事です。経営理念が浸透した状態が、企業文化が醸成された状態と同じ意味です。自社をどういった会社にしたいのか、その理想の姿が経営理念に込められ、それを浸透させられたら理想的な企業文化が醸成されていきます。
会社の中で最も仕事能力の高いのが社長です。基本的に小企業に勤める社員は、社長から言われたことしかしませんし、業務についてあまり深く考えてもいません。経営についてはさっぱりです。ですので、社長ご自身が考える業務での正しいあり方を経営理念に明文化し、それを浸透させることが大事です。
経営理念に基づいて作成された業務マニュアルが必要
私は、企業文化の醸成には、業務マニュアルが必須だと考えています。なぜなら、社員は理想とする企業文化を言葉で聞いただけでは、自分自身で考えて判断して行動ができないからです。
そもそも、小企業には自分で社長が考える理念を考察して判断して行動できる人はいないものとお考えください。そのような人材がいたら、すぐさま経営幹部に抜擢です。
さて、企業文化の醸成は、タンカーの方向転換のようなもので、同じ方向に舵を切り続け、そのうちゆっくりと方向が変わっていきます。そのため、社長の言動が朝令暮改であれば、いつまでも企業文化が根付くことはありません。
本田技研工業では、本田宗一郎や藤沢武夫の「業務の原理原則」となる言葉を社内報で伝え続け、直接の社員には一貫した指導をしていたと言われています。そのようにして立派な考えを持った社員が育っていくのだと思います。
とある雑貨屋チェーン店の業務マニュアル
とある駅ビルの雑貨屋さんのチェーン店で買い物をしたときに、社員がてきぱきと仕事をこなしているのを見て、「マニュアルがあり、教育を受けているのかな?」と思って訊ねてみたところ、「入社したときに数日の教育と、配属されてからの仕事を教えてもらう期間はありましたが、業務マニュアルはほとんど見たことがないです」と言われました。
あれだけ大きなチェーン展開をしている企業であれば、業務マニュアルがないはずがなく、膨大な業務マニュアルが作成されているはずです。そして、どの社員も同じ行動ができているので、全員が一定レベルの教育を受けているということは、業務マニュアルが企業文化になっている証拠でもあります。
会社が経営理念に基づいて運営されるということは、それに基づいて業務マニュアルが作成され、その業務マニュアルに基づいて業務が運営されている状態です。そして、その業務マニュアルは、一度出来上がったら終わりではなく、日々改善されていって、最善の考え方ややり方がつくられ続けています。その最善の考え方ややり方は、今現在で最高の生産性を出す方法ですので、それを社員全員が実施できたら、会社の利益も増えるはずです。
そのような社員全員の行動をマニュアルに基づいて行うように、社員を指導する立場の人が部門のリーダーと言えます。部門のリーダーは、経営理念を把握し、それを社員に教えることができることはもちろんのこと、それに基づいてマニュアルを最善なものに仕上げていくこと、マニュアルの変更があったらそれを関係者に知らせて、社員の働き方を更新することが任務になります。
業務マニュアルの醸成
最初は業務マニュアルの運用まで社長が面倒を見なければいけませんが、課長レベルのリーダーが育ってくると、その任務を彼らが引き継いでいきます。彼らには、あらゆることを業務マニュアルにして、会社の基準を作っていってもらいます。それが出来ない人を、課長などのリーダーに抜擢してはいけません。
そのうちに、膨大な業務マニュアルが出来上がっていくのですが、それが浸透していくと、誰も業務マニュアルを見なくても、その通りの高いレベルで業務ができるようになります。業務マニュアルは誰も見ることがなくなっていった状態が、「企業文化が定着した状態だ」と言えます。
ときどき、「マニュアルは無駄だ」とか「マニュアルで動くような社員ばかりになったら、いい会社はできない」と勘違いをされている方が、少なからずいらっしゃいます。そのようなマニュアルは、業務マニュアルとしてはレベルの低いものだと思います。
また、誰も見ない業務マニュアルを作成することが無駄なのではなく、小企業から中企業に成長させたい企業、チェーン展開をしていきたい企業にとっては、大事な作業です。
企業文化を醸成していくまでの流れ
企業文化をつくりたい企業は、大まかな流れとしては、まずは経営理念の策定を行い、それに基づいた各種基準を作成します。その基準を実現するための業務マニュアルを作成し、定着といった流れになります。
このときに策定する経営理念は、「正しい経営理念」であることが条件となります。正しい経営理念がどういったものなのかは、コラム「理念経営を実現する正しい経営理念と本物の経営理念」をご覧ください。
正しい経営理念ができたら、それに基づいた基準を作成します。基準とは、例えば次のようなものです。
- 自社にとっての顧客とはどのような人か?
- 自社にとって、いい社員とはどういった社員のことか?
- 自社にとって「きちんと働いている」とは、どういった働き方のことか?
先日、とある社長からの経営相談で、「社員がちゃんと働かない」とおっしゃっていました。社員に対して「お前たち、ちゃんと働きなさい」と指示を出していました。社員は、社員なりに企業文化に基づいてちゃんと働いているはずなので、「どうしたらいいのだろうか?」と悩んでいました。
社長と社員は、お互いに見ている基準が異なるので、社員との意見が合わないことが常です。
そこで、社長への質問で「社員がちゃんと働いた状態とはどういった状態のことですか?」と質問しつつ、役職毎の基準を作成していきました。
課長などのリーダー社員であれば、自ら経営理念や経営計画に基づいて目標を立て、部門の成果達成や社員の成長にも責任を持ち、業務を改善していけることが目標となります。
その社長は、社員に対して正しく指示が出せていなかったことを反省され、社員に期待することを明確に伝えられるようになりました。
この基準を示し続けていると、それを実現するための働き方が出来てくると思います。それを業務マニュアルにして、全員が一定レベル以上の業務ができるようにします。そうすることで、企業文化が醸成されていきます。
企業文化を変えたい場合
すでに社員数が100人を超えてきている企業の場合には、必ずと言ってよいほど経営理念が存在します。その企業が歴史のある企業であった場合には、経営理念に基づいているか、そうではないかは別として、すでに企業文化が定着しているはずです。
その会社をもう一段発展させたい場合、会社組織の成長が伸び悩んでいるのであれば、企業文化を醸成し直すことが必要です。
そのときに、経営理念の内容と企業文化が一致しているかどうかの確認が大事です。成長が止まってしまっている会社の場合、たいてい経営理念が間違っているか、経営理念の内容と企業文化が一致していないかのどちらかです。
前者であれば、経営理念を会社の規模や時代に合ったものに策定し直す必要があります。そして、経営理念に基づいた基準を作成し、企業文化のつくり直しをします。
後者であれば、経営理念を誰でも解釈ができるように、経営理念解説書を作成し、経営理念研修を実施して、我が社にとっての基準を作成し直していきます。
どちらにしても、社長にとっては多大な労力がかかります。なぜなら、通常の業務に加え、経営理念の造り直しの時間が取られるからです。経営理念の造り直しは、頭脳をフル回転させることになるので、とても疲れます。
ともあれ、社長お一人で考えても、考えがまとまらないものです。社長の側近に相談したとしても、やはり一社員の意見ですので、社長の考えからするとレベルの低いものになりかねません。そこで、経営理念コンサルタントを相談相手にする方法をおすすめします。
経営理念コンサルティングのご依頼・ご相談ごとがあれば、弊社までお気軽にご連絡ください。
この記事の著者

経営・集客コンサルタント
平野 亮庵 (Hirano Ryoan)
国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。
