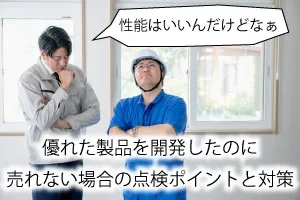
ビジネスをしていると、製品が売れなくて困る社長は多いと思います。いえ、困ったことのない社長はいないくらいです。
この記事でご紹介する、とある中小企業の化学薬品メーカーの社長も、そのお一人でした。
社長は、苦労の末にとても優れた化学薬品を開発しました。
その社長と2年ほど前に出会ったのですが、とある経営者セミナーに参加したときに、コンシューマ向け製品のサンプルを他の参加者に手渡している社長の姿を見た瞬間に、「売れなくて困っているのだろうな」と感じました。
社長に売れ行きを訪ねてみると図星で、「とても優れた製品を開発したのに、なぜ売れないのだろうか?」と感じていたようで、かなりお困りのようでした。
そこで、コンサルティング支援を提案させていただき、ご支援させていたくことになりました。
この記事では、当社のご支援事例を交えて、技術系社長が優れたBtoB製品を開発したのにも関わらず製品が売れない理由や、売れるようになるための基本や点検ポイント、実際に行なった売れる仕組みづくりの支援内容などをご紹介いたします。
同じような境遇の社長だけでなく、中小企業の社長をご支援されているコンサルタントにも参考になると思います。
特に技術系社長・開発系社長は、他人事ではなく「自分のことだ」と考えながらご覧ください。
優れた製品が売れない理由は?
社長は高い技術力をお持ちで、競合他社の製品と比べて何倍も効果が高く、身体に安全で、特殊用途からご家庭まで、あらゆるニーズ対応した化学薬品を開発していました。
ところが、20年以上経過して、倒産とはいかないまでも、想定していた事業規模には程遠い状態でした。
なぜ「売れていない」と瞬時にわかったのか?
コンシューマ向け製品のサンプルを手渡している姿を見ただけで、ほとんど売れていないことを図星で当ててしまったわけですが、自分では売れていない理由がわからなくても、他人から見たらすぐに見抜いてしまう場合があります。
マーケティングコンサルタントとしていろいろな社長をご支援させていただいていると、社長のPRしている姿を見るだけで、売れ行きが何と無く解ってしまいます。第三者目線で全体を見る、もしくは専門技術を追求してきたことで、「一事が万事」のように見えてしまうことがあります。
社長が部下を見ていて、「この部下はここで失敗するだろうな」と予想できてしまうことと同じです。
社長がサンプル品を配っている、どのような姿から売上を予想したのかと申しますと、サンプル品を「よかったら使ってください」とだけ言って手渡していたところです。
サンプル品を受取った人は、「ありがとうございます」の一言だけで、興味なさそうでした。
見ていられない性分の私は、失礼ながら社長からサンプル品を取り上げて、この製品がどれだけ素晴らしいものなのか、この製品を利用すると利用すると、生活がどのように便利になるのかをアドリブで伝えました。すると、サンプル品を受取った人が、「そんなに素晴らしい製品なのか。本当に頂いてもいいのか?」と価値を感じてくれました。
長年マーケティングコンサルタントをしていると、あらゆるジャンルのことに精通してくるので、製品と伝えている社長の姿を見ただけで、効果や性能の高さをある程度は瞬時にわかってしまうようです。
さらに、サンプル品の説明の最後に「効果を感じて気にいられたらホームページで販売しているのでご注文ください」とクロージングの言葉も添えておきました。サンプル品を受取られた方のうち、何人かがリピートしてくださるようになりました。
サンプル品をもらった人の受け取り方の違いに、社長は驚かれたようです。
技術系社長がよくはまる落とし穴
優れた製品が売れない理由で、まず考えられることは「優れた製品は売れる」という短絡的な発想による勘違いがあります。技術系社長は、その落とし穴にはまってしまう人が多いのです。
場合によっては、「売れない理由は、顧客がこの製品の良さを理解できないからだ」という、とんでもない発想をする社長もいます。この発想は、いわゆる「自己中」というものですが、お客様に対して疑心暗鬼になっている状態では、売れるものも売れなくて当然のことでしょう。
製品の性能は他社よりも優れていることは当然のことです。他社よりも性能が劣る製品を「我が社の製品は優れています」と言って売っていたとするならば、詐欺的な商売です。他社よりも優れた製品を扱っていることは、売れる要因の一つですが、売れるための要因はそれだけではありません。
優れた製品が売れるためには、その製品の魅力が、その製品を必要としている人に伝わらないといけないのです。製品の存在が知られなければ、その製品は存在しないことと同義なのです。
今まで何をして売れなかったのか?
冒頭でご紹介した社長は、5年ほど前に販売を強化すべく、社長の知り合いから紹介されたコンサルタントに支援を依頼されたそうです。そのコンサルタントは、大手メーカーで新規事業の立ち上げを行い、成功に導いた経験のある優れた人物でした。コンサルタントのアドバイスは、次のようなものでした。
- コンシューマ向け製品を開発
- ホームページを刷新
- YouTube動画を作成
社運をかけるくらいの気持ちで依頼され、コンサルタントのアドバイスに従ったようですが、さっぱり効果がありませんでした。
社長曰く、「コンサルタントのアドバイス通りにやったのに、さっぱり売れなかった」と述懐されておられました。コンシューマ向け製品を開発したのに売れない、ホームページを刷新したのに売れない、YouTube動画を作成したのに、売上は改善されませんでした。
販売でもPDCAが必要
社長はコンサルタントを信じて、言われるがままに施策を実施されましたが、その素直さは素晴らしいと思います。しかし、行ったことと言えば「照明器具のスイッチをONにしたら部屋が明るくなる」ということと似たような短絡的な発想でしたから、成果が出なくて当然です。
ビジネスはもっと複雑です。
施策をしてもその結果から何かを学び、目標達成の教訓を得て、次に活かしていく必要があります。つまり、PDCAサイクルを回し、改善していく必要があります。製造業であれば、製品開発や生産の現場では、生産性や安全などでPDCAサイクルを回して改善していくことをご存じでしたが、販売でもPDCAサイクルがあることをご存じではなかったようです。
ホームページは、刷新したら売れるようになるのではなく、売れるように刷新したら売れるようになるのです。「優れた製品を開発したら売れる」という短絡的な発想から抜けないといけません。
中小企業の社長に合ったやり方とは?
ここで、中小の社長が大手出身のコンサルタントに支援をしてもらったときに、よくある台詞をお伝えしたいと思います。その台詞とは、「それは大手のやり方だ」というものです。なぜ中小企業の社長は、コンサルタントのアドバイスにこのような台詞を言ってしまうのでしょうか?
それは、コンサルタントのアドバイスを、中小企業の社長はなかなか実施しないからです。イライラしたコンサルタントが、社長に詰め寄ると、「それは大手のやり方だ」となるわけです。コンサルタントは、社長にアドバイス通りに実施してもらえないと進展がありませんし、PDCAサイクルが回せないわけです。
進展がなければ解約されてしまう可能性があります。そのため、必死になって社長に「アドバイス通りにやって欲しい」と言うわけです。
その解決策はいくつもありますが、その一つとして「社長のやる気が出るように導くこと」です。社長の仕事は多岐に渡り、目先の仕事がどうしても優先になりがちです。それでも、未来についての施策をするためには、集中する時間が必要となります。そこで、やる気スイッチをONにしてあげることです。
営業戦略はいつ立てる?
ご紹介した社長は、幸いにもとても素直な方でしたから、「言われたことは何でもやってみよう」ということで、チャレンジされたようです。しかし、「ホームページやYouTube動画のことはよくわからないからお任せします」ということで、コンサルタントや制作会社に丸投げだったようです。そのような丸投げでは売れるようになるはずがありません。丸投げでは営業戦略どころではありませんし、丸投げされた制作会社は困ったことでしょう。
「営業戦略は必要ですか?」と問われ、「必要ありません」と答える社長はあまりいらっしゃらないと思います。
お客様の中には、「営業戦略は必要ありません」とおっしゃられる方にいらっしゃいます。そのお客様は、特殊なものを製造しているメーカーで、親会社から注文がきて、とくに新規営業活動が必要ない会社です。
そういった例外はあるとしても、技術系社長は営業戦略の必要性を理解していない場合が多いです。営業について勉強していない社長は、営業戦略を立てることよりも、大好きな開発をしていたい場合が多いです。その理由は理解できます。開発と営業は、まったく異なる能力を必要とするためです。ただでさえ忙しい社長ですから、勉強する時間もありません。
営業戦略は、販売の仕方を考えることではなく、会社の経営計画を立てることと同義とも言えます。中小企業では、営業と生産のバランスが最も大切なことですが、生産だけを計画するなら片輪走行をする自動車のようなものです。
社長が「会社の未来について考える時間がない」となると大問題のはずです。
ともあれ、販売で困っている会社では、資金繰りも困っていることが多いですから、コンサルティングのご提案のときに「売れるかもしれない」という期待感を持ってもらい、1年以内に「売れ始めた」という実感を味わってもらう必要があります。1年間耐えられない会社の場合は、まず資金調達からとなります。
製品が売れない理由を考える
最初の質問
製品が売れない理由をお考えいただくときに、最初に行なう質問があります。
- 本当に他社製品よりも優れているのか?
- 製品以外のところに売れない理由があるのではないか?
製品が売れない理由は、この2つのうちのどちらかです。
例えば、美味しい料理を出している飲食店があったとしましょう。その店主が、「他の店よりも味に自信がある」と言ったとしましょう。その場合、「他の店の味と、自分で比べてみたのか?」ということです。親しいお客様から、「この店は美味しい」とオベンチャラで言われることもあります。それが本心かどうかわかりませんし、本当に美味しい料理を出していたら行列ができてもおかしくはありませんから、真に受けてはいけません。その言葉に浮かれていたら、心がウキウキしている間に競合店が味を改善して、少しずつお客様が減っていきます。
自分で味を確かめて、本当に自分のお店の料理が美味しいのかを確かめるべきでしょう。
また、自分の味覚と、一般的なお客様の味覚に違いもあり、自分では「自分の店舗の味の方が美味しい」と感じたとしても、一般的なお客様からすると「コンビニの方が美味しいよね」となるケースもあります。ときどき試食会か何かを行い、市場を確かめることも大事です。
さて、競合他社よりも優れている製品を開発したことがわかった場合は、製品以外のところで負けていて、競合他社にお客様が流れていっている可能性もあります。
他社よりも優れた製品である場合の点検ポイント
製品が他社よりも優れているのに売れなくて悩んでいる会社は、次の項目の中でどれかに問題があります。社長に既存顧客を回っていただき、次のことをよくよく考えていただくようにしています。
- 価格は妥当か?
- 製品の見栄えはどうか?
- 製品の売り方はどうか?
- 顧客フォローはどうか?
これらのことは基本的なことです。その基本ができていなくて売れない場合があります。
お客様回りをして、これらのポイントをよくよく考えることができたら、売れていない原因が必ず見つかります。特にBtoBの商売をされている企業様はこのポイントをよくよく考えてください。
もう一度言います。よくよく考えるのです。
反対に言えば、これらの項目について、「何か1つのことをしたら売れる」というわけではありませんし、「まぁいいか」では売れないのです。普段からよくよく考えられていない場合、販売におけるQCやPDCAができていない状態なので、「お客様に言われたことだけを実施している」という状態です。
例えば、お好み焼き屋を開いて売上が増えなくて困っていたとしましょう。そこでお客様に「どのようなものを食べたいか?」と聞いて回ったところ、「お刺身を食べたい」「焼き鳥を食べたい」と言われたとします。お好み焼き屋なのに、「お客様に言われたから」ということで、お刺身や焼き鳥を出しても良いのでしょうか?
お客様の言われる通りにしたのに、事業本来のコンセプトから外れたことをしたら、お客様はさらに離れていくだけです。
お客様が離れていく場合は、「言われたことを対応してくれないから」ではなく、静かに離れていくものです。他にも求める価値を満たしてくれる企業はたくさんあるので、お客様は改善を求めることも面倒ですから、競合他社に静かに移っていくわけです。ビジネスは厳しいですね。
次に考えることは「顧客が何を求めているのか?」
販売力の強化や売上アップをご支援するときに、いつも社長にお伝えすることは、「お客様は製品を買ってくださるのではない。製品の働きを買ってくださるのだ」ということです。
例えば、冷蔵庫を購入した人がいたとしましょう。冷蔵庫を買った人は、表面的には冷蔵庫が欲しくて冷蔵庫を買ったのかもしれませんが、本当のところは「食材を長期保存したいから」とか、「冷えたビールや飲み物をいつでも飲めるようにしたい」といったことです。
このような、冷蔵庫を購入することで得られる恩恵のことを、ベネフィットといいます。お客様は、ベネフィットを求めて、たまたま冷蔵庫という選択肢を選ぶわけです。
化学薬品を販売するのであれば、その化学薬品が持っている働きをPRし、コンシューマ向けには生活がどのように変わるのかもPRすることが大切です。
中小企業の社長のよくある勘違いとして、「ブランディングをしたい」というものがあります。ブランディングは大手がするもので、中小企業がブランディングをしても、広告宣伝費をムダに使ってしまうだけです。その高い費用を、私に預けてくださった方が、よほど売上高を増やしてみせます。「ブランディングだ」と称して、製品名を一生懸命PRしたところで、テレビCMをしている大手製品に勝てるはずがありません。
基本がしっかりできて売れるようになったらステップアップ
ビジネスには売れるための基本がありますが、その基本から外れたことをしている部分を発見し改善していくことのスタートです。上記のような基本について、他社が出来ていて自社が出来ていない箇所がないか、色眼鏡をかけないで見てよくよく考えることです。
よくよく考えることが苦手な方は、当社にご相談ください。スポットでダメ出しコンサルティング支援をさせていただきます。徹底的にダメ出しをするので、覚悟なさってください。
出来ていないことを改善して出来るようにすれば、優れた製品ならば必ず売れるようになります。そして、お客様の気持ちが少しずつわかるようになり、自信が付いてきます。目先の利益を得て社長に資金繰りに対して安心感を得ることもできます。
そうなったら、より多くの費用が払えるようになるので、次なるステップに進んでいただきます。次のステップは、自社や自社事業の存在理由を考えることや顧客設定の見直しです。それに基づいたソリューションの改善や開発を行います。
話を戻したいと思います。
売れる仕組みの構築
さて、冒頭の社長に対して、「私が具体的に何をしたのか?」ですが、まず面談を何度も何度も繰り返して、次のことを順次行いました。製品を顧客目線で訴求ができていなかったことに加え、製品は売りっぱなしで、顧客フォローも貧弱でしたから、売れる仕組みの構築から入りました。
- 製品群や業務内容の全体像の把握
- バリューチェーンや業務フローの把握
- 未来ビジョンの明確化
- 当社のセミナーの定期参加(小さな会社の社長のためのセミナー)
- 製品を求める顧客や、その顧客が求める価値の明確化
- 増収増益の仕組みづくり
- ホームページの刷新
- 総合カタログやチラシの制作
- 営業トークの改善
まず、どのように事業活動が行われているのかを把握し、その中でお客様無視の部分や競合他社よりも劣っている部分が無いかを点検しました。それが、「製品群や業務内容の全体像の把握」と、「バリューチェーンや業務フローの把握」です。
それらを分析した中で、私がボトルネックに感じたことは、一言で「売り方」のところでした。具体的に何をしていくのか、目標やご支援内容、スタッフの具体的な行動、それらの施策にかかる費用と支払いのタイミング、販売代理店の数や収益の増加予想等を余すことなく企画書にまとめました。ちなみに、企画書は50ページを超えました。
未来ビジョンの明確化
未来ビジョンを明確にした理由は、社長のやる気を引き出すためです。未来ビジョンを聞き出すときに、社長がどういったところでやる気スイッチが入るのかがわかります。売上が落ちている社長は、気持ちが沈んでいることが多く、気持ちが高まってもすぐに落ちることも多いので、やる気スイッチを入れ続けることが必要になります。
やる気スイッチは社長によって違います。「ゴルフがしたいから」とか「銀座で飲みたいから」というモチベーションは論外ですが、「社員の幸せのために」と涙を流される社長もいらっしゃれば、「我が社で開発した技術で世界中の人たちを幸福にしたい」と熱く語られる社長もいらっしゃいます。そういった利他のやる気スイッチが入るところを発見したら、折に触れて話題を振って熱く語ってもらうようにしています。
当社のセミナーの定期参加
続いて、当社のセミナー(小さな会社の社長のためのセミナー)に定期参加していただいている理由は、顧客マインドや仕事の仕方を改めてもらう必要があったためです。社長に「顧客に対しての考え方が違っています」と直接言ったところで、考え方がいきなり変わることはありませんし、反発される恐れもあるので、セミナーの定期参加をしてもらっています。
「製品を求める顧客」や「その顧客が求める価値の明確化」、「集客の仕組みづくり」は、今まであまり考えてこられなかったようなので、ここは時間をかけました。ここで4~5時間の打ち合わせと称する「質問攻め」を10回以上行ったと思います。社長は考えることを続けられたので、毎回ヘトヘトになったと思います。
製品を求める顧客や、その顧客が求める価値の明確化
今までの対象顧客は、製品を購入してもらった企業だけでした。潜在顧客や製品の導入を依頼したエンドユーザのことは、あまり考えたことがないようで、ベネフィットを理解されていないようでした。商社を通じて販売することが多かったので、商社廻りはされていましたが、エンドユーザの声を直接拾ってはいなかったようです。また、「商社に卸しているのだから、販売は商社がやるもの」と、とんでもない発想をされておられました。
そこで、私自身が製品の導入を検討している人やエンドユーザになり切って質問していきました。また、既存の販売代理店のフォローを行っていただきつつ、顧客ニーズを聞き出してもらうように促しました。
施工代理店は何社から契約をしていましたが、日本全国に施工代理店が存在しなかったので、施工代理店の新規募集を行うことにしました。施工代理店の数が倍に増えたら、売上高も倍に増える可能性があるからです。
次に、施工代理店の数を1年後に2倍に増やす計画を立てました。
増収増益の仕組みづくり
計画を立てるだけでは施工代理店は増えませんから、施工代理店の新規募集の仕組みや、新規販売代理店がすぐに販売活動ができるようにする仕組みを考えました。
具体的には、ホームページでの募集を行い、応募があれば手っ取り早く施工代理店として営業活動ができる体制を整えました。製品の使い方を教える講習会の開催や施工代理店向けの機材販売、販売支援の仕組みづくり、エンドユーザの声をフィードバックするといった仕組みなどを考えて具体化しました。
また、2日間で施工方法を覚えられる研修を組み立てて、どのように開催していくのかを支援いたしました。初回の研修では、私自身が講師として対応し、どのように講習をしたらいいのかを、社長に実地で見ていただき、研修の仕方を学んでいただきました。セミナーや講習の企画・実施は当社の強みでもあります。
ホームページの刷新
次にホームページの刷新を行ったわけですが、その理由は、既存ホームページからのお問い合わせ件数がゼロだったからです。以前のホームページは、コンシューマ向け製品を開発した直後に制作されたものでしたから、コンシューマ向けの訴求が中心でした。しかし、売上の大部分は、明らかに業務用製品でしたから、刷新をしていただきました。
ちなみに、ホームページ原稿の作成はすべて私が一人で行い、社長にチェックをしてもらう流れにしました。ホームページ原稿の作成はとても時間がかかりますし、率直に言って営業力に問題のある社長が作成したところで、スペック寄りの話題になり、売れるホームページにはならないからです。
そもそも、中小企業がコンシューマ向け製品を開発し、ホームページで訴求したところで、売れるはずがないため、既存ホームページは対象顧客が間違っていたわけです。売れない理由は簡単です。コンシューマのほぼ全員が、化学薬品を欲しいと思ったときは、ネット検索するのではなくドラッグストアに行くからです。
当初、ホームページを刷新したときに、コンシューマ向け製品の訴求はしない方針を考えていました。ところが、社長のご要望で「せっかくコンシューマ向け製品を開発したのだから、それも訴求したい」ということだったので、そのご意向を尊重しつつ、BtoB製品や施工代理店募集を訴求できるものにしました。
実のところ、コンシューマ向け製品の訴求を残しておいたことが、後に功を奏しました。コンシューマ向け製品の販売数は、ホームページを刷新してから1年後には30倍ほどに増えたので、「これだけ売れているのですよ」と業務用製品をお求めの方に訴求ができるという相乗効果がありました。
当社は強力なSEO対策とコンテンツの量産を得意としているので、それも実施いたしました。今現在のアクセス数は、刷新前と比較して100倍ほどに増え、ホームページ経由でのお問い合わせ件数は、以前のホームページは3年間でゼロ件だったものが、今では月に10件ほど入るようになりました。大手メーカー様からのご相談も毎月のように入るようになり、施工代理店も毎月1件ずつ増えています。
総合カタログやチラシの制作
総合カタログやチラシの制作ですが、もともとチラシや会社案内は制作されていたようですが、そのチラシの活かし方がわからなかったようです。そういったことで、「わからないからお任せで」ということで、費用をかけてチラシを制作されたようです。しかし、ほとんど配られることはなく、チラシの在庫の山を何年もかかえていたようです。
ここで新しくチラシを制作したわけですが、チラシテンプレートを活用して、格安で仕上げること。そして、チラシのデザインを顧客が求めるソリューションに合わせてデザインの種類を取りそろえること。さらに、施工代理店がそのデザインを活用できるようにしたことです。
具体的には、コンシューマ向け製品のチラシ、化学薬品の活用方法のチラシ、企業向けのチラシといった販促ツールのデザインをターゲット層ごとに制作し、それを施工代理店が利用できるようにしました。すると、たくさん印刷しなくても良いですし、チラシの在庫をかかえることもありません。施工代理店では、必要に応じてカラー両面印刷をしたら良いわけですから、すぐに販売活動ができます。
チラシに続いて総合カタログも製作しました。これは、格安のオンデマンド印刷にて小ロットを制作しました。業務用製品は、用途別に数種類開発されていましたが、すべての製品が一覧になっているカタログが存在しませんでした。施工代理店に出来上がった総合カタログを年末のご挨拶のときに渡してもらったところ、「このような用途の製品があるとは知らなかった。もっと早く言ってくれていたら・・・」ということもあったそうです。社長は製品の存在を伝えたつもりになっていたのですが、施工代理店の社長は把握していなかったようです。
悪いのは施工代理店の社長ではありません。訴求方法を誤っていた社長が悪いのです。こうったケースは、よくあることです。
人は知りたいことのみを知りたいと感じるもので、こちらから伝えたい場合はタイミングがあるのです。口頭だけで伝えたら、伝わるものも伝わりません。口頭で伝え切れなかったことを、カタログに語ってもらうわけです。これからは、施工代理店がすべての製品を把握してもらえるようになったので、機会損失を阻止することができます。
営業トークの改善
営業トークの改善では、話すことよりも、聞くことを中心にお教えし、ロールプレイングを繰り返しました。しかし、ロールプレイングと実際とでは、感じがつかめないこともあります。そこで、ホームページから新規お問い合わせがあったお客様の営業に何度か同行させていただき、私自身が社長に代わって実際に営業を行い、クロージングまでして見せ、訴求の流れを把握してもらいました。
また、社長には当社のコーチング研修に参加していただきました。今までの営業活動では、自分の話したいことだけを話したり、商社には「もっと製品を売ってもらいたい」と伝えるかのどちらかだけでした。コーチングスキルを身につけていただき、質問をしながら相手の気持ちや本音を理解できるようになっていただきました。
以上が支援内容の全容です。もともと製品力があったので、製品を求める人がどういった人なのか、何に困っていて何を欲しているのかを考え続け、しっかりと訴求することで集客ができるようになります。
ただし、私のやり方は地味で地道な方法ですから、「何か手っ取り早い方法を教えて欲しい」という社長には不向きな内容です。ご支援させていただいた社長は、私の親ほどのご年齢で体力も落ちているはずですのに、素直によく対応してくださったと思います。それだけ未来ビジョンの実現を強くお考えなのだと感じました。
ここまでが第一段階で行なったことですが、ご支援を開始してから1年以上かかりました。
社長は、私からすると親子ほどの年齢差があります。そのような私から、いろいろな要望を出していますが、ムチャなアドバイスを聞き入れてくださり、精力的に行動されています。その結果が現れてきているものと思います。
現在は、さらなる増収増益のために第二段階に進んでいる状態です。
製品を売るのではなくソリューションを売ること
製品が売れるためには、他社よりも優れた製品を開発することが条件の一つなのですが、優れた製品が持っている価値や、それが生み出す問題解決を売ることが大切です。その問題解決策のことを、ソリューションといいます。
特に、今まで知られていない製品を販売するのであれば、製品が持っている働きを考え、その働きを必要としている人に向けて訴求するわけです。
例えば、業務用抗菌剤を販売していたとすると、食品工場であれば「菌数を減らすこと」はもちろんのことですが、それだけではありません。食中毒を出さないこと、食品にカビが入らないこと、ニュースにならないこと、検査機関からの指摘が無いことといった問題や課題があります。
そういった社長がかかえる問題や課題を解決できる方法を訴求することが大切です。問題や課題の悩みが大きい人ほど、「待っていました」とばかりにご購入くださいます。ソリューションを売り続けていたら、事業内容も変化していって、より付加価値の高い製品やサービスが生まれます。
販売で成功する方法は、営業トークを身につけることではありません。お客様に問題や課題が解決できることを誠実に伝え、可能性を感じてもらうことです。そのためにも、お客様にとっての問題や課題が何かをつかむ必要があります。つまり、営業トークよりも質問力で、お客様の問題や課題を把握することが大事です。
ともあれ、まずはお客様に出会うこと、お客様とコミュニケーションを取ることが大切になります。総合カタログやチラシを作成した理由は、ソリューションを伝えることもありますが、コミュニケーションのきっかけづくりのツールでもあります。
ただ単にお客様に会いに行くだけでは、邪魔者扱いをされる可能性もあります。お客様と会う時間は10分でも良いわけです。そのときに総合カタログやチラシを渡したら、話のきっかけが作れるので、そのときにコーチングスキルを活用して、お客様から問題や課題を引き出し、その解決策をお客様に認識してもらうことです。すると、お客様も聞き耳を立てているはずですから、成功率の高い販売がスタートします。製品の販売は最後です。
まとめると次の流れになります。
- 話のきっかけづくり
- 問題や課題の発見
- 解決策の提案
その後に解決した後をイメージしてもらうと、よりクロージングがしやすくなります。導入方法や費用は、興味のあるお客様から質問として出てきますから、そのタイミングで説明すると良いと思います。
ホームページ経由でお問い合わせがあった場合には、製品の良さはある程度伝わっているので、解決策の提案はほどほどにしつつ、自社製品が他社よりも優れていると言える客観的な事実を少し伝え、製品やサービスをトータルでどれだけお客様のお役に立てるのかを訴求すると良いでしょう。
以上、技術系社長が開発した優れたBtoB製品が売れない場合の対策を解説いたしました。個別具体的には、それぞれの企業様で施策内容は異なると思いますが、基本的なことは同じです。
中小企業の社長をご支援するときは、すべてやってあげるくらいの支援をしないと、前進していかないことが多いので、とても手間がかかりますが、優れた製品を開発しておられる場合には、増収増益が早いです。
ここでご紹介した社長にご提供したサービスは、次の通りです。
- マーケティング・集客戦略立案
- 事業内容を集客できるように改善
- Web集客コンサルティングと集客ホームページ制作
- 営業等への同行
- コーチング研修や小さな会社の社長のためのセミナー等のご参加
当社にて行っているマーケティングコンサルティングは、クライアント企業様が集客のボトルネックとなっている箇所やミッシングリンクが起こっている箇所のスパース対策を行っています。当社のコンサルティングの特長は、中小企業に限定されますが、経営を全体的に見てスパース対策ができることです。
優れたBtoB製品を開発したのにも関わらず製品が売れなくて困っている社長は、ぜひ当社にご相談ください。
この記事の著者

経営・集客コンサルタント
平野 亮庵 (Hirano Ryoan)
国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。
