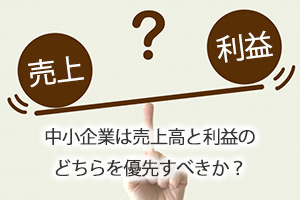
会社を経営していて、何らかの方針を出したときに、売上高と利益の両方がアップしたら、それに越したことはありません。
しかし、経営はうまくいかないことが多く、売上高が増えたのに利益が下がってしまうこともあれば、その逆に売上高が下がったのにもかかわらず、利益が増えることもあります。
中小企業の社長から、ときどき「売上高と利益のどちらを優先すべきか?」ということを聞かれるので、何らかの回答をしたいと思います。
結論から述べると、「経営判断による」というものです。
「売上高と利益のどちらを優先するのか」の、さまざまな経営判断の考え方を述べたいと思います。
利益とは?
最初に、利益とはどういった種類があるのか、損益計算書に出てくる利益についてご説明したいと思います。利益の種類によっては、経営判断や方針が異なるからです。
損益計算書に出てくる利益には、主に次のようなものがあります。ここでは、厳密な名称や解説は避けたいと思います。
- 売上総利益(粗利益)
- 営業利益
- 経常利益
- 税引前利益
- 純利益
それぞれの利益の意味
売上総利益は、売上高から原価や外注費、製造にかかった水道光熱費、消耗品費などを引いたものです。原価を安く仕入れて高く売ることが商売の基本です。また、製造の生産性などによって、売上総利益が増えます。
ここで、売上総利益が低くなったのであれば、原材料費や製造に携わる人材の人件費の高騰、外注費の増加などが挙げられます。
営業利益は、売上総利益から販売費と一般管理費を引いたものです。販売費とは、営業担当者の人件費や広告宣伝費などです。一般管理費とは、製造や販売に携わっていない人の人件費や家賃、製造に関係のない水道光熱費などです。
販売費と一般管理費を合わせて、販管費と言われます。
営業利益は、通常の営業活動を行って残った利益です。この利益が大きくなることが、漠然と「利益を出したい」と考えている社長の目標の一つとなります。
他の利益については、別途ご説明したいと思います。
売上高が増えたら利益も増えるのか?
単純に考えると、売上高が増えると利益が増えるように思われます。利益率が一定であれば、そのようになります。
しかし、経営では常に、事業規模相応の想定外のことが起こります。
例えば、売上高が増えた結果、社内の仕事がてんてこ舞いになり、生産性が下がって、残業代が増えて、利益が下がってしまうこともあります。
他にも、仕入れが増えてしまって、「別の値段の高い業者から仕入れることになってしまった」という場合もあるかもしれません。
売上高が増加することの意味
売上高とは、簡単に述べると、お客様から商品やサービスが認められて、お金を支払ってくれた金額の総合計です。売上高が増加するということは、それだけ市場に対する影響力も増します。
例えば、美味しいケーキを売っているお店があったとします。美味しいケーキはよく売れるようになるので、売上高が増えていきます。その利益でもって、多店舗経営をしていったとします。そのようにして、市場規模を増していくことができます。
そして、いろいろな地域にお店を出しているケーキ屋さんは、「美味しいのではないか?」という期待感があります。その期待感で商品が売れるようにもなります。そのようにして有名店になっていきます。
ケーキを買いたいと思っているときに、有名店と無名店が並んでいたとしたら、私のようなもの好きであれば無名店で買うかもしれませんが、一般的には有名店の方のケーキの方が選ばれると思います。
売上高が増加するということは、それだけ市場への影響力を高めることができます。企業によっては、市場の影響力を増すために、多少利益を落としたとしても、売上高の増加を目指すという方針を立てる場合もあります。
市場への影響力を高める施策のことを、「ブランディング」と言います。
ブランディングをするということは、ロゴを刷新したり、かっこいいチラシを作ったり、自動車をラッピングすることだけではありません。それらは、ブランディングの一側面しか見ていないことになります。話が反れてしまいましたが、ブランディングの正しい考え方については、「中小企業のブランディングの考え方」をご参照ください。
売上高を増加させるためには、良いものを作り、その良さが見込み客に訴求されることが基本中の基本です。
利益が増加することの意味
売上高から経費を引いたものが利益です。売上総利益が増加するということは、原価を安く仕入れることができたり、生産性を高めたりすることができたりしたことを意味します。
また、売上総利益が増加しなくて営業利益が増加したのであれば、営業の効率が上がったり、一般管理費を節約できたことを意味します。つまり、経営が効率化されたことを意味します。
利益が出ると、その分だけ社員にお給料を増やしてあげることができる可能性があります。また、利益を研究開発に投入することができるようになります。
ケーキ屋さんを経営して利益が出ると、その利益を利用して新商品の開発がしやすくなります。季節物の開発を行って、大々的にPRすることもできます。ケーキを製造する機械を導入することもできます。
そのように利益が増えることによって、それを投資に回すことができたら、さらなる売上高や利益の増加につなげることができます。
利益を増加させる方法によっては、反対に利益を下げる場合がある
ここで、短絡的に「原価を下げたらいいのだな」とか「営業の費用を下げたらいいのだな」と考えたら、売上高が下がってしまう恐れがあります。その結果、利益が下がってしまいます。
また、ケーキ屋さんの例でご説明しましょう。
美味しいケーキを販売して、売上高が増加していったとします。経営者が、利益があまり出ていないことに気が付いて、「製造原価を削減しよう」と経営方針を打ち出したとします。その結果、ケーキの味が変わってしまって、不味くなり、ケーキが売れなくなってしまう可能性があります。
はたまた、社長が「営業利益を増加させたい」と考え、店頭スタッフの人数を削減する方針を出したとします。すると、店舗前で行っていた試食会ができなくなり、新製品を出してもそれを見込み客に訴求し切れずに、売れ残りが出るようになってしまったらどうでしょうか?
売上高だけとか、利益だけを目標にすると、その結果、真逆のことが起こってしまう可能性があります。経営計画を立てるときには、机上の空論で理想を語るのではなく、マーケティングの知識も必要となります。
当社では、売上高だけを求めて「売上~、売上~」と言い続ける病気のことを、「売上病」と呼んでいます。また、利益だけを求めて連呼する社長の病気を、「利益病」と呼んでいます。売上病や利益病の社長がときどきいらっしゃるので、その治療薬を出すことも、私どもの仕事でもあります。
経営者は、「利益の増大だけを考えたら、売上高を下げてしまい、その結果利益も下げてしまうことがある」ということを、覚えておいてください。
ですので、会社の経営では、「売上高を増やしつつ利益も増やすこと」という具合に、売上高と利益の2種類の目標を掲げ、それを実現するため経営方針を立てることが大事です。
売上高の下げ幅と利益の下げ幅の関係
売上高の下げ幅と利益の下げ幅は異なります。例えば、売上高が10%下がってしまったら、利益がどれだけ減ってしまうのでしょうか?
「利益も10%ほど下がる」と考えたら、経営のセンスが疑われてしまいます。
変動費と固定費でご説明したいと思います。
変動費と固定費
変動費とは、売上高に比例して変動する費用のことです。ケーキ屋さんの例では、小麦粉や砂糖などの製造原価です。簡単に述べると、原材料を購入したときの費用です。
固定費とは、売上高が変化しても変動しない費用のことです。人件費や地代家賃などが固定費になります。
ちなみに、ケーキ屋さんの水道光熱費はどうでしょうか?
ケーキ屋さんの場合、ケーキを焼くのに電気代やガス代がかかりますし、水道もたくさん使うと思います。そこで、変動費に入れることが望ましいと言えます。
当社のようなコンサルティング企業の水道光熱費は、季節変動はあるものの、固定費として扱います。
売上高が減ったら利益がどれだけ減るかの試算
さて、ケーキ屋さんで、固定費が100万円、売上高が300万円、変動費率が50%だったとします。300万円の売上高に対して、変動費が150万円ですから、経費が固定費と変動費を足して、合計250万円となります。売上高から経費を引いた残りの利益が、50万円となります。
さて、ここで売上高が10%下がってしまったとしましょう。300万円の10%は30万円ですから、売上高が270万円になってしまいました。
変動費は、270万円の50%ですから、135万円です。経費は、固定費が100万円と変わらずで、変動費が135万円。合計235万円です。すると利益は、売上高270万円から経費の合計235万円を引いて、35万円になります。
売上高が10%下がったら、利益が50万円から35万円に減ってしまったので、30%も減ったことになります。売上高が下がってしまったときに、その割合が思ったよりも小さくても安心できないことを意味します。
もし、前期と今期を比べて売上高が下がってしまったのにも関わらず、利益が増額していたら、内部の経費削減を相当行ったことを意味します。そのことが、さらなる売上高の減額に繋がらなければ良いのですが。
売上高が下がり、利益が増加した社長に対してどう思うか?
ここまで解説してきたなかで、おおよその答えを出したものと思いますが、重要なことをもう少し加筆したいと思います。
以前に、「今期は前期と比べて売上高が下がってしまったが、なんとか工夫して利益を残すことができた」と述べられた社長がいらっしゃいました。
この社長の言葉には、いろいろな論点があります。
売上高を下げてしまったことによる市場に対する影響力は?
売上高が下がっているということは、先ほど述べたように市場原理によると、影響力を下げてしまったことを意味します。
竹田陽一先生のランチェスターの法則ではありませんが、市場の影響力は、2乗で利いてくるとお考えください。例えば、市場の影響力が半減すると、売上高が1/4に減ってしまう場合もあるのです。
しかし、業界全体が縮小しているのであれば、業界の縮小率と自社の売上高の減少率を比べてみて、売上高の減少の方が小さければ、もしかしたら市場規模を増やしている可能性もあります。
効率よく経営をする良い機会となる
売上高が減っても、赤字にしなかったことは、社長としては偉いと思います。内部の生産性を高めたわけですから、その生産性が維持できたら、売上高が増大したら、利益はその伸び率以上に増えるはずです。
零細企業や小企業の場合は、売上高が下がっても、利益を調整する幅は割と多いです。例えば、社長が夜に外出する機会を減らせば、その分だけ利益が出ます。売上高の減少は、社長が無駄遣いをする癖を改めるいい機会でもあります。
私を含め、社長が反省をする機会は、売上高が下がって赤字になりそうなときです。会社が従業員を雇うぐらいの規模になってきたら、少しずつ社長の公私混同を戒めていかないといけません。
第三者から見て、「このままでは赤字に転落する」と思われても、利益が出ているときの社長はイケイケゴーゴーになりやすいです。社長は、私のような口の悪いコンサルタントの話が聞けるぐらいの度量を持ってください。
利益を出す構造にすべき
中小企業では、毎年利益を残さないで、経費で使い切ってしまうことを旨としている会社が多いですが、当社がご支援する企業で、将来的に大きな会社にしたい場合には、そのようなことは許されません。
投資をする場合、銀行からお金を借りたら早いのですが、資本を蓄えてそれを投資に回して、事業を拡大していくことが安定経営の基本です。
「利益が出たら、税金を払わないといけないじゃないか」と言われることもありますが、利益以上に税金を持っていかれることはありませんし、会社に現金が残ると、物理的にも精神的にも会社経営が安定しやすいです。
そして、投資をしていったら、その投資が売上高や利益の増加に直結しているのかを確認することも大事です。理想は、資産の伸び率よりも、売上高の伸び率が高いことです。そのためには、高収益商品の開発や生産性の向上が大事です。
中小企業は売上高と利益のどちらを優先すべきか?
いろいろと述べてきましたが、最後にこの記事をまとめたいと思います。
「中小企業は売上高と利益のどちらを優先すべきか?」ということですが、基本的には両方を同様に優先させるべきです。そして、売上高と利益に関わる別の経営目標を立てて、それを実現する経営方針を立てるべきです。
売上高を目標とする場合であれば、売上高そのものを目標としても良いですし、販売数量を目標としても良いと思います。利益の目標であれば、売上総利益や営業利益を目標としても良いですし、労働生産性を目標としても良いと思います。
そして、その2つが両立するように方針を立てます。
企業の方針によっては、多少利益を落としたとしても、市場の影響力を増すために、売上高の増加を目指すという方針を立てる場合もあります。「あと少しの売上高増加でナンバー1企業になれる」という場合は、そのようにすべきでしょう。
ただし、ナンバー1企業になることが目的ではないことをお忘れなく。お客様に良い商品やサービスを提供するという目的を見失ったら、慢心してしまったり、目標を見失ったりして、ナンバー1の地位が瓦解する可能性があります。
零細企業や小企業では、売上高が下がっても利益の調整は比較的簡単にできます。その場合では、売上高と利益のどちらを優先すべきかは、私は「利益だ」と思います。売上高が下がっても、利益が出るようであれば、資金調達の必要性はありませんし、現金が回っていたら倒産もしないからです。
以上、経営目標を立てる場合に、売上高と利益のどちらを優先すべきかについて、述べてまいりました。経営計画を立てる上での参考になれば幸いです。
この記事の著者

経営・集客コンサルタント
平野 亮庵 (Hirano Ryoan)
国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。
