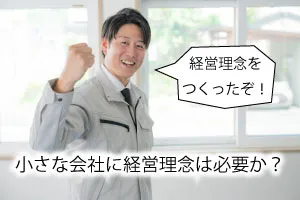
結論から述べるならば、小さな会社のまま事業拡大を行わないのであれば、立派な経営理念を必要としません。
この「立派な」というところが、この記事のミソになります。
小さな会社と言っても、社長お一人の会社から、100人規模の会社まで、小さな会社の定義にもよります。
従業員数が30人を超えてきて、社長が直接従業員の指導ができなくなってくるようであれば、経営理念を策定していく段階です。
この記事では、小さな会社を経営されている社長が初めて経営理念を作ろうとするときの考え方をご説明いたします。
経営理念とは?
そもそも経営理念とはどういったものでしょうか?
この定義はなかなかできるものではありません。なぜなら、社長によって定義が異なるからです。
多くの社長が思っていらっしゃる経営理念とは、「会社の思想・信条などを一言で表したもの」だと思います。
しかし、別の社長からすると、「その一言は、経営理念ではなく『社是』である」と考える方もいらっしゃいます。また別の社長は、「その一言は『企業理念』である」とおっしゃる方もいます。
さらに、「経営理念は、何かの一文ではなく、自社が信条とすることを箇条書きにしたものである」と言われる方もいらっしゃいます。
このように、社長によって経営理念の定義がバラバラなのです。
実際に、1,000社以上の経営理念を調べてみると、会社が生まれた時期によって定義に流行と思えるような傾向はあるものの、本当に定義がバラバラでした。創業が古い企業の場合は、「社是」や「社訓」という言葉が使われる傾向があり、新しい会社は「パーパス」や「ミッション」といった横文字が使われる傾向が見受けられます。
このように、会社によってバラバラ、社長の考えによってバラバラの経営理念ですが、当社としては、どのように考えているのかと言いますと、「どのような定義でも良い」と考えています。
要するに、経営理念の名称に何を使ったとしても、経営理念をつくる目的は、社員全員が心を一つにして進むべき方向や立派な社員像を示し、社会に貢献する立派な会社をつくることです。それが達成できるのであれば、どのような名称でもかまいません。
初めてつくる経営理念はどのような内容にすべきか?
どのような社長でも、初めて経営理念を作るときは時間がかかります。
どのような経営理念を作れば良いのか悩んでしまいますし、作ったとしてもそれが本当に経営理念なのだろうか悩みます。
出来上がった経営理念を社員に伝えても、社員の表情は冷ややかなものです。
そうして、考え抜いて作成された経営理念は、お蔵入りするわけです。
ですが、社員の表情が冷ややかであったとしても、正しい経営理念であれば、ぜひとも浸透させ、社員の意識改革をしていただきたいと思います。
経営理念に含めるべき3要素
最初につくる経営理念は、次の3要素が含まれているものであれば、できるだけ簡潔なものにしつつも、内容は何でも良いと思います。
- 我が社の存在理由
- 我が社の事業内容
- 我が社が目指していること
我が社の存在理由とは、「何のために我が社が存在しているのか?」という問いに応え切ることです。
例えば、当社の存在理由は、「お客様の会社を立派な会社にすること」です。
次に、我が社の事業内容です。これは、我が社の存在理由から導き出すことができます。
例えば、当社であれば「立派な会社にすること」ですから、立派な会社の定義をすることで、事業内容が決まります。立派な会社の会社は、経営理念があり、社員のEQが高く、お客様から信頼を得て、集客もしっかりできて、競合他社との競争に勝ち、財務体質も良い会社のことです。個人企業から中小企業までを対象として、立派な会社にしていくためのソリューションを提供しています。
事業内容の決め方には、中小企業であればランチェスター理論からして、絞り込みをした方が良いでしょう。また、絞り込みをしていてナンバー1企業になったとしたら、さらなる事業拡大を考えるのであれば、企業の成長に合わせて経営理念を進化させていくことも考えられます。
そこが、「我が社が目指しているもの」になります。
我が社の存在理由や事業内容、目指しているものを一言でまとめても良いですし、一言と説明文でまとめても良いと思います。
本田技研工業の最初の経営理念
私は、本田宗一郎先生や藤沢武夫先生を敬愛しているので、本田技研工業の経営理念の進化について調べました。本田技研工業の初めての経営理念は、名称が「社是」で、内容は次の文章でした。
わが社は、世界的視野に立ち、顧客の要請に応えて、性能の優れた、廉價(廉価)な製品を生産する。わが社の発展を期することは、ひとり從業員と株主の幸福に寄與(寄与)するに止まらない。
良い商品を供給することによって顧客に喜ばれ、関係諸会社の興隆に資し、さらに日本工業の技術水準を高め、もって社会に貢献することこそ、わが社存立の目的である。
これが制定されたのは、1956年(昭和31年)です。本田技研工業創業から9年目のことで、まだスーパーカブは開発されておらず、売上高はピークから30%ほどもダウンし、倒産の危機の真っただ中でした。ライン生産をしているメーカーが、売上高が30%もダウンしたら、大変なことです。
その中で、我が社の存在理由を「自社のためではない、日本のためなのだ」と明確化したのです。そして事業内容として、「オートバイ」と記載されていません。現在の本田技研工業の経営理念には、「モビリティ」と記載されていますが、当時は「儲かれば何でもやる」という意味ではなく、「エンジンを通じて世界を変える」という考えでした。ですから、本田技研工業では、耕うん機も開発していました。
そして目指すものは、世界であることが明確になっています。
別の会社の経営理念を真似しても良いのか?
ときどき、経営理念の内容で相談されることとして、「尊敬する経営者がいて、その会社の経営理念を真似しても良いのか?」というものや、「親会社の経営理念を踏襲したいのだが、親会社の社長から『オリジナルの経営理念をつくりなさい』と言われたが、どうしたらいいのか?」というものがあります。
そういった、別のところから持ってきた経営理念のことを、私は「借りものの経営理念」と呼んでいます。
借りもの経営理念を導入するための条件
「借りもの経営理念はどうか?」ということですが、結論から言いますと、利用しても良いです。ただし、条件があります。
経営理念は、社長を含む全社員がそれに従って行動しなければなりません。つまり、社長よりも上位概念なのです。社長はいずれ引退していきますが、会社が残るとすれば、経営理念が残るわけです。
立派な社長によって立派な経営理念がつくられるわけですが、それが創業の精神として後世に残されて、新参企業と経営理念の良し悪しの戦い、生き残り戦が行われるわけです。より優れた遺伝子が、後世に残っていくわけです。
そういった意味で、経営理念は進化が求められます。経営理念の進化については後述いたします。
さて、別の会社の経営理念を真似しても良い条件ですが、それは
その経営理念に社長ご自身が心から共感し、その経営理念の実現に率先して行動し、社員に経営理念の内容をわかりやすく説明ができるか?
従うことができるのであれば、それを経営理念に掲げても良いでしょう。従えないのであれば、経営理念はヘタに掲げるべきではありません。
経営理念を導入する目的は?
社長が経営理念を作成する目的として、「社員を働かせたい」というものがあります。悪く言えば、社員の給料はそのままに、たくさんの成果を出してもらいたいというものです。
そういった目的の経営理念は、社長自らが経営理念に従わないことが多く、社長は治外法権となりますから、そういった会社の場合は経営理念を掲げない方が良いです。
なぜなら、自分が出来ないことを社員に押し付けるわけですから、搾取の精神です。社員は社長が言っていることと行動の違いに矛盾を感じます。いずれ会社が崩壊していくか、一定の規模よりも大きくならないことになります。
そういった搾取の会社では、社員のお給料を成果と連動しやすくして、高いお給料を払って働いてもらった方が良いと思います。そうすることで、成果を出せる社員だけが残っていきますが、社員は矛盾を感じることなく、経済的な幸福感に従順になって働くことができます。
借りものの経営理念で立派な会社を創った偉人たち
「経営理念は社長自ら作らないといけない」と言われることが多く、私もその方が良いと考えます。その理由な、「社長が自分で作ったものなので、自分が従うことができるから」です。
しかし、多くの社長は言語化や文章化が苦手ですから、自分で経営理念を作らない人もいます。先ほどご紹介した、本田技研工業の経営理念も藤沢武夫先生が作ったものです。稲盛和夫先生も、初期の頃の経営理念やスローガンは、中村天風先生の書籍の内容をほぼそのまま流用されているところもあります。
ところが、本田宗一郎先生や稲盛和夫先生が偉いのは、他人が作った経営理念を自分の言葉として社員に解説していったことです。つまり、自分よりも上に置いているのです。
経営理念を「とりあえず」で掲げても良いか?
とりあえず作成した経営理念を掲げてもようかどうかですが、結論から述べるならば、掲げても良いです。
経営理念は前向きに進化させていくものですから、とりあえず掲げた経営理念が都合が悪くなったら、前向きに進化させれば良いのです。
「経営理念をコロコロ変えては、格好が悪い」と思われるかもしれませんが、経営理念を護って会社の成長を止めてしまっても良くはありません。自分の立派なプライドを護るよりも、立派な会社にする社長が、立派な社長なのです。
そして、「いずれ変更される経営理念を掲げる」ということですが、経営理念を掲げ、それを浸透させていくという、初めてのチャレンジを社長が行うわけです。そこに、確実に失敗することが予定されています。その失敗を乗り越えて、立派な会社に改革していくための修行とも言える人間関係の問題を解決していって、社員の心を一丸と変えていくわけです。
要するに練習が必要ですから、とりあえずでも良いので、早く経営理念を掲げた方が良いと思っています。
零細企業なのに「世界一を目指す」などの大きな目標を掲げても良いのか?
経営理念の進化は、前向きに進化させていくことをお伝えしました。「前向き」とは、社長の経験や経営哲学、信条、宗教観などの進化によって、より次元の高い経営理念に進化させることです。
「今まで日本一を目指していたが、世界企業にするぞ」と言っても、何かで日本一になったことのない社長が言ったところで、誰も信じてはくれません。実績も伴って進化していくものです。
本田技研工業が「世界的視野に立ち」と掲げたときは、売上高は日本一でしたから、説得力があります。しかし、本田宗一郎は、創業間もない町工場のレベルの、一流でもないオートバイを製造していた時代でも、「いいか、オレたちは世界一のオートバイを創っているのだ」と、熱意を込めて社員に語り続けていたわけです。
「社長がどれだけ本気に取り組んでいるのか」ということもありますが、考え方や行動において世界一のものがあれば良いと思います。
中国のことわざに「嘘も100回言ったら真実になる」というものがあるそうです。嘘をつくことはよくありませんが、目指していることを100回言って、それに向けての社長の行動力のすさまじさを目の当たりにした社員が、「世界を目指していることは本当かもしれない」と考えるようになるわけです。
何をもって世界一とするのかは別途あるとしても、世界一を目指すのであれば、社員にはその根拠を行動で示すことが大切です。
「世界企業を目指すぞ。目標を掲げるのは社長の仕事で、実施するのは社員の仕事だ。あとはお前たちでやれ」というものでは、誰も社長についていかないことでしょう。目標を立てることは、社長の役割の一つですが、それだけでは会社は大きくなりません。
経営理念の進化
経営理念を進化させるときは、前向きに進化させていくわけですが、「何をもって前向きか?」ということが疑問に思われたかもしれません。
目指すものだけを取ると、目標となる売上高を上方修正することも前向きな進化ですし、県内でナンバー1を目指していたものを、日本一を目指すように変更することも、前向きな進化だと言えます。
また、経営理念には目指すものだけではなく、それを実現させるための方法も記載していくべきです。その方法は、会社の事業規模によって進化していきます。その方法を進化させていく社長は、経営に熟達すると言いますか、経営力がアップしていっているはずですから、より高度な経営理念をつくることができるわけです。
そして、最終的にはとても抽象的な言葉となって経営理念が完成していきます。
この進化の過程を考えると、最初に作られる行動指針は単純な内容かもしれませんし、業務マニュアルとも言えるものかもしれませんが、少しずつ進化していき、その途中で業務マニュアルと経営理念が分かれていき、経営理念をさらに昇華していくものと思います。
会社の成長過程でおおよその業務マニュアルのようなものから経営理念に進化していく過程をまとめると、次のようになります。
| 会社の規模 | 経営理念の内容 |
|---|---|
| 個人企業 | 社長個人が目指すものとモットー |
| 零細企業 | 社長個人のモットー、自社の存在理由と目指すもの |
| 小企業 | 社長個人のモットー、自社の存在理由、未来ビジョン、行動指針あいうえお |
| 中企業 | 基本理念、未来ビジョン、経営指針、行動指針(借りもので良い) |
この過程は、必ずこのステップを踏むものではなく、要するに良いカルチャー(企業文化)が根付き立派な会社に進化しているのであれば、この限りではありません。
これらの項目について少し解説いたします。
個人企業
個人企業は、個人事業主か社長お一人の法人、もしくは家族が手伝ってくれている規模です。そのような会社は、社長の言葉が絶対ですから、経営理念としては「社長個人が目指すものとモットー」だけで良いです。
社長個人が目指すものとしては、「いずれ世界企業にするぞ」というものを掲げていただいてもかまいませんが、それを誰かに言ったところで「ムリだ」と否定されて落ち込むだけですから、信頼できる経営コンサルタントの先生のみに相談するだけに留めておいてください。
次に社長のモットーですが、これは「自分は、絶対に嘘はつかない」とか「お客様を最優先に行動する」といった、事業活動についてのモットーです。このモットーは、正しいものであれば会社は成長します。そして、従業員を雇って、そのモットーを伝えて、社長に代わって成果を出してもらうように導いていきます。
そのようにして事業規模が成長を始めたら、その規模に応じて進化させていけば、会社は成長し零細企業、小企業へと成長していきます。
零細企業
零細企業は、親戚や知り合いなどに手伝ってもらっている段階です。零細企業になると、社長個人のモットーは個人企業のときよりも洗練されたものになります。なぜなら従業員を指導していかないといけないためです。
社長お一人の個人企業であれば、モットーは社長の頭の片隅に置いておけば良いわけですが、従業員が増えてくるとモットーを明文化し、そのモットーに基づいて業務マニュアルを作成していく段階になります。
そのときの会社は、社長の言動で従業員が振り回される状態です。社長が朝言っていたことと夜言っていることが異なる場合もあります。完全なYesマン、もしくは言われたことだけをやる従業員だけが生き残れる規模です。
零細企業で会社の規模が成長することを止めて、今の規模を維持するだけであれば、社長のモットーのみを明文化するだけで良いと思います。いえ、従業員数が3~4名ほどであれば、言葉で伝えるだけでも良いと思います。
さらに事業規模を拡大させていく場合は、モットーの明文化と進化、そして「自社の存在理由と目指すもの」を明確にしておくことが大切です。
自社の存在理由と目指すものが明確になっていると、「社長についていったら、人のために貢献できてうれしいし、自分の将来も豊かになる」と思って、会社の変化に耐えてついてきてくれる人が出てきます。
従業員の中で、古参の人か、1つ先輩が新人教育を担当することになりますが、そのときに業務マニュアルを少しずつでも良いので作成していってください。業務マニュアルは、経営理念とは言えませんが、社長が考えているモットーが新人に伝わるようになります。
社長が考えているモットーに基づいて、業務マニュアルを進化させていくことで、改善カルチャ―を根付かせることもできます。やはり、改善をするにしてもモットーといった基となる考え方が必要なのです。
小企業
小企業にまでなってくると、社長個人のモットーは洗練されたものになります。項目数も多くなっている場合もあります。そして、自社の存在理由はそのまま利用するとして、社長が小企業まで成長させたことによる自信が出てきますから、「将来、我が社をこうしたい」という未来ビジョンを抱き始めます。
未来ビジョンは、「いずれ、こういったことを実現したい」というものです。例えば、排気ガスを浄化する脱臭装置などを開発しているメーカーであれば、「いずれ、世界中の煙突から有害な煙を無くしたい」といった最終的に実現したいことです。
世界中の煙突から有害な煙を無くしたら、それで未来ビジョンの達成ですが、それまでに段階があります。例えば、県内のシェアナンバー1になる。といったものもあります。それらの中間的な目標に期限を決め、どのようにそれを実現するのか、そのための予算はどうなるのかを明文化したものを経営計画とか事業計画といいます。
小企業になってくると、立派な会社では、経営計画や事業計画は社長の思いつきや、行き当たりばったりで決まるのではなく、経営理念から策定されます。そのように作成された経営計画や事業計画は、より説得力が高まります。
そして、全社員が「これだけは守ってもらいたい」という行動指針ができます。最初の行動指針は、5つぐらいの項目でかまいません。当社では、それを「行動指針あいうえお」や、「行動指針いろは」といったような、誰でも取り組みやすそうな名前を付けることをすすめています。
行動指針あいうえおであれば、例えば、「あ、あいさつは元気よく。い、いつもニコニコ笑顔で対応」といったものです。
小企業の従業員の中には、こういった基本的なことすらできていない人が多く見受けられます。特に、零細企業からの古参社員ほどそのようです。ですから、社長自らが行動指針あいうえおの実践者となり、従業員の模範とならないといけません。
もちろん、行動指針あいうえおの5項目が出来るくらいでは、立派な会社だとは言えません。行動指針の内容も、事業規模に合わせて項目を増やしたり、内容を洗練させたりして、前向きに進化させていくことが大切です。そして、進化させたときには、全従業員にそのことを伝えて、社長自らが解説をするようにしてください。その解説する姿を見た従業員の中から、成長していった人材が、経営担当者として迎えられます。
中企業
小企業の段階で社長のモットーが洗練され、それに基づいた業務マニュアルが完備されていき、従業員が社長に代わって成果を出せるように業務を遂行できるようになった段階です。
そして、小企業から中企業に進化していく過程では、業務マニュアルに基づいて業務を行い、部下を育成できるマネージャーが育っています。マネージャーの中から成長意欲のある人を中心として経営担当者に育成していく必要があります。
小企業までの経営理念では、従業員が成果を出し、マネージャーまで育てられる内容になっているはずですが、経営担当者に育てていくためには物足りません。
そこで、次のものすべてを最初の経営理念として策定します。
- 基本理念
- 未来ビジョン
- 経営指針
- 行動指針(借りもので良い)
基本理念とは、呼び方は会社によって異なりますが、当社の定義では自社の事業経営の概念を一文で表したものです。当社では、「泥中の花」という基本理念をかかげています。
この基本理念の中に、自社の存在理由や事業内容、目指すものなどが入っている一文です。「泥中の花」を紐解くと、存在理由しか入っていません。そういった基本理念の場合には、別途事業内容や目指すものを制定して、基本理念を補完します。
未来ビジョンは、今現段階のものでかまいません。社長の経営の実力が高まってくると、より遠くのより大きな未来ビジョンがありありと見えるようになります。それが見え、「ぜひとも実現させたい」、もしくは「将来、我が社を継いでくれる人材に実現してもらいたい」というものを強く思うようであれば、未来ビジョンを変更するときです。
ちなみに、松下幸之助先生は250年計画というものを立てられたそうです。
経営指針とは、経営担当者が社長に代わって経営判断をするときに基準とすべきものです。箇条書きで表されることが多く、例えば、スティーブ・ジョブス先生が好みそうな「ハングリー精神」とか、佐伯勇先生が好みそうな「日々新又日新」というものも考えられます。
豊田綱領には経営指針に当たるものが5項目で述べられています。5番目の「神仏を尊崇し、報恩感謝の生活を為すべし」とあります。
よく理念経営をされている会社は、欧米の経営学者からすると「カルトだ」と言われることがありますが、会社の理念の中枢に「神仏を尊崇し」と残しているトヨタ自動車は、さすがとしか言いようがありません。
偉人の人ほど、この項目が哲学的で、数が少ない傾向にあり、古い会社では「社訓」という言葉で定義されていることが多いです。本田技研工業では、「わが社の運営方針」という名称で5項目が制定されています。
行動指針は、「行動指針あいうえお」から進化したものです。行動指針は「借りもので良い」とありますが、京セラフィロソフィーのように、立派な会社ほど項目が多くなります。このようなたくさんの項目をいきなり作成することはできませんから、最初の行動指針はどうしても借りものにならざるを得ないようです。
当社では、通称「IngIngフォーマット」と呼んでいる、行動指針フォーマットがございます。当社の経営理念コンサルティングでは、IngIngフォーマットを利用して、社長の考えを盛り込み、言葉を入れ替えるなどして、行動指針として完成させるサービスを提供しております。IngIngフォーマットを導入することで、行動指針の導入が短期間でできます。
例えば、稲盛和夫先生の場合は、最初の経営理念は、中村天風先生の内容をほぼそのままパクッていました。ただし、流用したとしても、その内容を社長自信が従業員に説明ができるようになっていないといけません。パクッてきた経営理念を従業員に伝えて、社長が知らん顔していたら、従業員はその経営理念に従うはずがないからです。
いくら経営理念の内容が立派であっても、社長がその経営理念に忠実に生きて立派な社長でなければ、従業員はその経営理念に従うはずがないのです。また、経営理念に忠実に生きていない社長は、そもそも従業員が経営理念に忠実に生きているかどうかは、気にも留めないと思いますが・・・。
さて、借りものの行動指針であっても、運用していくと都合が悪い部分、足りない部分が出てきます。その都合の悪くなった部分、足りない部分は、修正したり加筆したりして、行動指針を進化させていってください。
そのように進化させていくためにも、経営指針の中に、「日々新又日新」といった日々成長していくことを促す内容を入れておくべきでしょう。豊田綱領は、そういった全方位的な内容が含まれている最高峰の経営指針とも言える内容です。
経営理念を作り始めたい社長は何をしたらいいのか?
経営理念をご自身で作ることができる社長は、本当によく本を読んで勉強なさっている方です。経営書はもちろんのこと、哲学書や経典などもよく読まれて、そこから教訓を得て、経営に活かしている方です。
しかし、私は「本をたくさん読みなさい」とは言いません。
本当は読んでいただいた方が良いのですが、私は何度読んでも勉強になる数冊ほどの良書で良いと思います。
そして、経営理念を作り始めたい社長に、ぜひおすすめしたいことがあります。それは、毎日何かの教訓を得る機会があると思います。
本を読んだり、ビジネスセミナーに参加したりして勉強し、「なるほど」と思ったことをメモするわけです。
他にも例えば、社員が時間のミスをしてしまったとしたら、「ミスをしない工夫を、手間のかからない方法で何重にもすること」とメモできます。新商品を開発し、意外にもよく売れたら、その勝因は何だったも、経営に関する教訓です。
そのような小さなことでも良いので、手帳などにメモしてください。
それが100個、200個と溜まってくると、そこから事業活動で成果を出すための教訓をまとめることができます。その内容を経営指針や行動指針に仕上げることができるわけです。内容が重複しても良いので、1日1つの教訓を書くことにチャレンジしてみてください。
そして、ミスした社員といっしょに原因追及と改善策を考えつつ、教訓を伝えるわけです。
その教訓を活かして、その後の事業活動の改善につなげます。
例えば、得られた教訓が「お客様の時間をできるだけ奪ってはならない」というものがあったとしましょう。すると、お客様への返事を送らせてしまったら、お客様の時間を奪うことにもつながりますから、「出来るだけ早くご返答をするように努める」ということで、従業員も考えて業務を行うようになります。
こうすることで、経営理念をつくるための能力が上がっていきます。
社長の中には言語化や文章化が苦手な社長は多いです。そういった社長は、経営理念コンサルタントかビジネスコーチに質問をしてもらって、言葉をまとめてもらう方法もあります。
そういった他人に頼る方法を取ったとしても、社長の中にボキャブラリがなければ経営理念の完成にはなかなか完成には至りません。やはり、普段から教訓をまとめる練習をなさってください。
以上、小さな会社の経営理念の必要性について述べました。
まとめると、最初の経営理念は、経営理念と言えるものではないかもしれませんが、必要であること。経営理念は、社長の成長や事業規模の拡大によって、前向きに進化していくことです。
そして、会社の規模に応じたおおよその経営理念の姿を明らかにしました。
「経営理念をつくりたい」とお考えの社長は、ぜひ当社の経営理念コンサルティングをご利用ください。
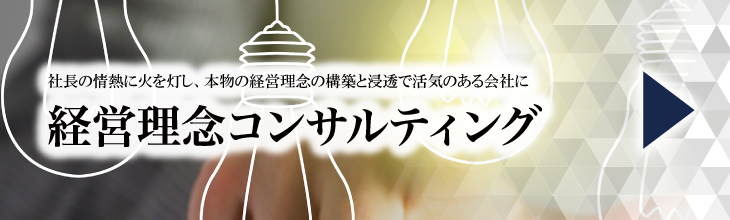
この記事の著者

経営・集客コンサルタント
平野 亮庵 (Hirano Ryoan)
国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。
