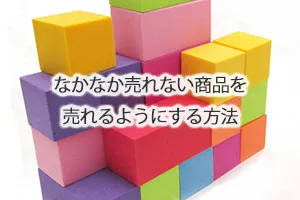
商品を開発した人は、たいてい「これは売れる」と思って開発します。しかし、なかなか売れなくて地団駄を踏んでしまうこともあります。
商品を開発した企業様から、当社に「売れるようにしてもらいたい」と、時折ご相談をいただくのですが、すぐに売れる商品となかなか売れない商品があります。
売れない商品が売れるようになるためには、条件があります。なかなか売れない商品を売ることは大変そうですが、条件に合えば実のところ思ったよりも簡単に売れることもあります。
その条件を解説するので、開発した商品が本当に売れないものなのか、何かを変えたら売れるようになるのか、何をどのように変えたらいいのかを解説いたします。
商品の売れ行きの傾向
商品の需要には変化があり、すでに世間的に売れている商品を発売したときはすぐに売れますが、世間的に売れていない商品、新しい価値の商品はなかなか売れません。
小企業は世間一般に売れているものを販売すること
小さな会社であれば、世間一般に売れているものを開発した方が良いです。しかし、テレビなどで「最近はこの商品が売れている」と発表されたものは、その後1年以内には売れなくなることがほとんどですから、手を出してはいけません。
例えば、タピオカブームが参考になります。当社の近くに、いくつかのタピオカ屋さんが開業しましたが、1店は、オープンと同時に閉店していました。他のお店は、別の食品を販売して生き残っています。
世間的に売れていない商品、まだその価値が広く知られていない商品は、なかなか売れません。そのような商品には、将来の需要が見込める商品と、見込めない商品があります。
将来の需要が見込める商品の場合は、人口構造の変化や消費者の認識の変化を待つ必要があります。これらの変化を待たないと売れない商品の場合は、いくらPRを繰り返しても、なかなか売れませんから、PRの費用は完全にはムダにはなりませんが、「糠に釘、暖簾に腕押し」と感じることでしょう。
人口構造の変化による需要の変化
人口構造の変化とは、ある範囲内の人口構造が少しずつ変化していくことです。
例えば、小さな子供が増えている地域があれば、いつの間にか保育園が増えます。そのうちに、子供が大きくなってきて、保育園に閑古鳥が鳴き出し、学習塾が流行りはじめます。そのように人口構造が変化していくと、その範囲内の需要が変化します。
人口構造の変化はとてもゆっくりで、なおかつ確実に起こるものです。人口構造の変化に合わせて、自社の事業構造を変化させていくことが大事です。
認識の変化による需要の変化
認識の変化とは、範囲内の人々の認識が少しずつ変わっていくことです。
例えば、一部の天然の塩は健康に良いとされていますが、60代以上の方々は、「塩は健康に悪い」という認識を持っている人が多くなります。私は塩を積極的に食べるようにしていますが、70代以上の方は減塩生活をされている方が多いです。
20年ほど前であれば、減塩のものが多く並んでいたと思います。ところが、最近のスーパーマーケットで調味料を見ていると、「減塩」と書かれたものをあまり見かけなくなりました。そのように、少しずつ人々の認識が変わってきて、いつの間にか認識が変わっているものがあります。
20年前に「天然塩の健康的なお味噌」を開発したところで、それはまったく売れませんが、今現在ではそのような商品が選ばれるようになったわけです。
人口構造の変化や認識の変化は、とても時間がかかるので、社長によほどの思い入れや熱意がないのであれば、小企業が手を出してはいけない領域です。
商品の多品種化と多角化
多角化と言えば、アンゾフの戦略マトリクスが有名ですが、ここでは一倉定先生が述べられていた「多品種化と多角化」を解説いたします。
商品開発には、多品種化という方向性と多角化という方向性があります。この方向性を初めて指摘された方は存じませんが、一倉定先生の書籍で学びました。
多品種化とは、既存顧客に新商品を投入することです。多品種化とは、既存商品を別の業界に販売することです。
どちらが売れるのかということですが、すでに販売チャンネルが開いている多品種化の方が、容易に売れます。
多品種化
私はBtoBのWebマーケティングを得意としており、ご契約したお客様は、ほぼすべてのお客様にて売上アップに貢献できています。そのため、とても信頼していただいています。
そのお客様にもっと利益を出してもらいたいと考えているので、ビジネスマッチングにも取り組んでいます。先日も、ビルメンテナンス企業様に、新技術の塗装を開発された企業様の商品をご提案させていただきました。
そのようにして、私自身が得意とするWebマーケティングのコンサルティング支援だけでなく、ビジネスマッチング支援もしています。
このようにして、当社のサービスは付加価値を高める工夫をしています。
多角化の難しさ
多角化には、他業界特有の販売ルート開拓やルールの把握などが必要となりますから、新しい販売方法を習得しなければなりません。このことは、とても労力がかかります。
私鉄に電気機器を販売している小さな商社が、日本を代表する鉄道会社に新規開拓をしようとしました。大手鉄道会社は、新しい商社との取引は、いろいろな事情からとても警戒します。そして、お百度を踏んで、ようやく小さな取引から始めてもらえました。
ところが、もともと取引をしていた大手商社が、常識ではありえないような安値交戦を仕掛けてきました。その結果、小さな商社では利益が出せなかったため、今までの努力も虚しく撤退していきました。
多角化では、そのような業界特有のルールを学んでいくことになります。
商品の点検
売れていない商品は、次の4つのうちのどれかをまず点検します。これらの4つのものが悪ければ、価格に見合った商品とは言えなくなり、売れなくなるからです。
- 原材料
- スキル
- 見栄え
- 売り方
原材料の点検
原材料が悪いと商品の品質に影響する場合があります。
例えば、生パスタのお店であれば、「デュラム小麦がおいしい」ということが一般的です。私はあまり味に対して良し悪しはわかりませんが、味に敏感な人であれば、すぐに原材料の良し悪しを見抜いてしまいます。
スキルの点検
スキルは、職人としての腕前のことです。いくら良い原材料を使ったとしても、出来上がりの品質が腕前によって左右されます。
とある駅の駅前に、古びた老舗のパン屋さんがありました。そこに有名なパン屋さんが出店してきて、老舗のパン屋さんはいっきに顧客が奪われてしまいました。そのパン屋さんは、どうしたらいいのでしょうか?
お店の引っ越し、改装といったことをやっても、焼け石に水です。引っ越しをしたところで、またその近くに有名なパン屋さんが引っ越してきてしまったら大変です。その有名なパン屋さんよりも美味しいパンを提供するか、撤退のどちらかです。
見栄えの点検
見栄えの点検では、お客様から商品がどのように見られているのかを、客観的に感じることが大事です。
しかし、客観的にはなかなか自分の判断ができないようです。その理由は簡単で、固定観念です。
例えば、今、この記事をオフィスやご自宅で見られている方であれば、周りを見渡してみてください。目の前には、物がいろいろと置かれていることと思います。その物の中で、1年以上、同じ場所に置かれているものは、目の中に入っていない可能性があります。
捨てられるに置かれ、山積みにされた資料は、典型的だと言えます。毎日目に入っているのにもかかわらず、そこに存在し続けているのです。
売り方の点検
原材料や品質、見栄えが良くても、売り方が悪ければ売れません。売り方には、主に次の3つに分類されると思います。
- PRの方法
- お客様とのコミュニケーション
- お客様のフォロー
PR方法については、少し長くなるので後ほどご説明します。お客様とのコミュニケーションでは、愛想の良さが主なものです。
先日、クリニック開業コンサルの先生とお食事をさせていただき、美容皮膚科で成功しているクリニックについて教えていただきました。その先生の持ち前の明るさと、診療内容の解説の判りやすさ、お客様フォローのレベルの高さを解説いただき、「なるほどな」と思いました。
クリニック開業コンサルの先生曰く、「クリニックの集患は、開業場所の立地の良さと医師の愛想の良さで決まる」と教えていただきました。もちろん、他にも集患の要素はありますが、基本的にその2つです。
顧客目線でこれらの点検を行うことで、本当に売れる商品になるのか、斜陽商品なのかを見極めることができます。ポイントはお客様の立場です。改善できる箇所があれば、価格を下げる必要はありませんし、付加価値が高いものであれば高い価格でも売れるはずです。
商品ではなくソリューションを売る
有名なマーケティングの書籍で「ドリルを売るなら穴を売れ」というものがあります。自分で壁に穴を開けて壁に絵を掛けたいと考えている人は、ドリルを買いたいのではなく、穴を開けたいわけですから、穴を売った方が良いという比喩です。このタイトルを眺めているだけでも、自社商品が売れない理由が判ります。
私がよくセミナーで解説する内容として、「冷蔵庫を買いたいと思っている人は、冷蔵庫が欲しいわけではない。洗濯機を買いたいと思っている人は、洗濯機が欲しいわけではない」というものがあります。
おかしな話に聞こえますが、実際にそうなのです。
冷蔵庫を買いたい人は、食材を手軽に冷やすことができるもの、食材を長期保存できるものを探しているわけです。その結果として、価格や手軽さ、便利さなどを考慮した結果、「冷蔵庫が欲しい」ということになるわけです。
洗濯機も同様です。消費者は洗濯機が欲しいわけではなく、洗いものを手軽にでき、時間を生み出せるようにしたいわけです。
冷蔵庫であれば「物を冷やす」、洗濯機であれば「衣類を洗濯する」ということが直接の求められているメリットになりますが、それによって得られる付加価値というものがベネフィットになります。消費者は、実はベネフィットを求めている場合があります。
自社商品が売れていない場合に、自社商品のスペックを熱心に伝えようとする営業担当者もいますが、消費者はそのようなものに興味はなく、「自分のお困りごとを解消してくれる商品、要望を満たしてくれる商品は無いだろうか?」とソリューションを探しているわけです。
先ほど、ビルのメンテナンス会社様のことを話しましたが、その企業様が提供するサービスは、季節変動がありました。その季節変動を埋めつつ、全体の売上高を高めるために、当初はWeb集客コンサルティングをさせていただいたのですが、やはりどうも閑散期の売上高が高まりませんでした。
そこで、閑散期のみに取り組めて、始めやすくて利益になりやすい別事業をご紹介したわけです。すると、「ぜひ話を聞かせて欲しい」ということで、マッチングができたわけです。
商品ラインナップを増やす
先ほど、多品種化のことを述べましたが、「枯葉も山の賑わい」といいますが、商品は単品で売れなかったとしても、複数の商品ラインナップを揃えることで売れるようになる場合があります。
単品販売では事業になりにくい
単品販売とは、一つの商品のみを販売することです。
例えば、豚骨ラーメン屋さんであれば、味は一種類のみのお店が多いと思います。それに対して、中華料理店ではラーメン以外にもチャーハンや餃子、野菜炒めといった料理も提供しています。
吉野家の牛丼は、牛丼一筋で全国展開をしました。そのような例外はあるものの、基本的に単品では事業になりにくいです。先ほど、お客様はソリューションを求めていることを述べましたが、単品ではソリューション提供がしにくくなります。また、単品で飽きてしまったら、お客様がいっきに減ってしまったりするからです。
タピオカミルクティーのみを単品販売していた販売店は、ブームによってどの店でも行列ができていましたが、今では行列ができているお店はほとんどありません。
単品でも、一定数の熱狂的ファンができれば事業化が可能ですが、うまく事業化された例は少ないです。
基本的には、商品ラインナップを増やすことで、ブームに左右されることなく、一定の売上高が得られるようにすることが大事です。
消費者は比較して買いたい
コーヒーショップのサイズに大中小があるように、立ち食い蕎麦屋に天そばやきつねうどんがあるように、いろいろな商品があることで、比較して選ばれる業種もあります。
立ち食い蕎麦屋の店長が、「舞茸天ぷら蕎麦の味に自信があるから」といって、その商品だけしか販売していなければ、昼間でも顧客数がゼロの日が続くことでしょう。
ラインナップを増やしていくことで、選んで購入できるようにすると、商品が売れるようになることがあります。
その場合は、やたらと増やすのではなく、スクラップ&ビルドが大事です。スクラップ&ビルドとは、人気のない商品を減らして新しい商品を追加していくことです。商品点数が多くなり過ぎると、消費者は反対に選べなくなってくるからです。
商品はPRしなければ売れない
商品が売れない典型は、PRが不十分であることです。
単品商売であったとしても、商品の魅力が消費者にしっかり伝われば、リピート顧客となっていくはずです。
PRの方法
PRの方法は、業種によって異なります。
先ほどクリニックのお話しもしましたが、クリニックであれば立地条件の良い場所に開業して、看板を出すことです。
BtoBビジネスであれば、展示会に出展したり、DMを送ったり、ホームページで自社商品やサービスの魅力をしっかり訴求することです。
PRの方法でよく質問されることは、「ホームページを制作したら売れるようになりますか?」「チラシを撒いたら売れるようになりますか?」といった、ゼロ点か100点の二択の質問です。「ホームページを制作したら、どの程度集客ができるようになりますか?」が正しい訊き方です。
ホームページを制作したら売れるようになるかどうかは、やってみないと判りませんが、Webマーケティングに精通している人であれば、経験や情報などからどの程度売れそうなのか分かります。
しかし、ホームページ集客という高度な技をWeb集客コンサルタントやWebマーケティング会社に任せるのではなく、ホームページ制作会社に求める人もいて、やってみた結果「良かった」とか「ダメだった」という具合に、ゼロ点か100点といった2種類の判断しかできないことが多いです。それがダメなのです。ホームページ制作会社は、ホームページ制作のプロであったとしても、ホームページ集客のプロではないことをご留意ください。
PRは自社の命綱でもありますから、しっかり研究をして、自社オリジナルの集客手法を構築していくことが大切です。ゼロ点か100点の判断はダメで、他人任せ業者任せにしないで、社長が全責任を持って研究し、0点だと思ったら「なぜ悪かったのか?」を十分に検討し、再挑戦を何度か行うことが大切です。
チラシを撒くとしても、どの地域にどの程度撒くのか、どれくらいの頻度で撒くのか、どの程度撒いたらどれくらい集客できたのか、といったことを分析して、ノウハウを貯めていくことが大切です。
ホームページ集客の方法と業者の選び方
少しだけ、ホームページ集客の方法を解説したいと思います。具体的な施策方法は、業種や企業の営業スタイルなどによって異なるので、Web集客コンサルティングをご依頼ください。
集客ホームページ制作では、次の流れで行います。このステップを踏むことで、ホームページ経由での集客ができます。
- お客様のご事情の確認
- Webマーケティング分析
- ホームページ集客企画立案
- (場合によっては商品の改善)
- デザイン案
- 既存ホームページ改修 or 新規ホームページ制作
- ランディングページ制作(LP制作)
- SEOコンテンツマーケティング
- アクセス解析/SEO順位解析による改善
- 営業ツール作成/改善
- 営業担当者養成
この流れでも勘所は、Webマーケティング分析とSEOコンテンツマーケティングです。
Webマーケティング分析によって、どれくらい集客ができそうか、その集客のためにどれくらいの費用をかけないといけないのかを分析します。費用対効果が判れば、それだけホームページ集客のリスクを下げ、効果を高めることができます。当社では、ホームページ集客で費用対効果が合わないと思った企業様は、ご支援をお断りするようにしています。
SEOコンテンツマーケティングとは、ページを量産してSEO対策を行い、たくさんの検索キーワードで上位ヒットさせ、オーガニック検索からの集客をする手法です。LPと組み合わせることで、成約を高めることができます。
弊社がご支援させていただいたBtoBビジネスの企業様では、今まではホームページからまったくお問い合わせが無かったところが、「見積もりが欲しい」と買うことを前提としたお問い合わせが増え、驚かれることが多いです。ホームページ集客に成功したら、そのようになります。
さて、Web集客コンサルティング会社やWebマーケティング会社に依頼しないで、直接ホームページ制作会社に依頼すると、上記の中のデザイン案からスタートします。すると、「デザインが美しい」とか、集客とは直接関係の無いところで議論が進んでしまい、集客のところが見落とされてしまいます。
さらには、ホームページが完成して公開されたら終了ですから、その後はクライアント企業から依頼があれば、言われた通りの修正をしていくだけになります。
ホームページ制作を依頼した企業は、ホームページ集客の手法を自ら勉強して経験していかないと集客ができません。ですから、ホームページ集客の専門家を自社で雇わない限り「ホームページでは集客ができない」という結論に至ってしまうのです。
以上、さまざまな角度で売れない商品を売れるようにするための方法について解説いたしました。どのような条件で売れないのかを分析し、改善していってください。
特にPRの方法では、「SNSをやったがダメだった」とか「ホームページを制作してもらったけれども良かった」という具合にゼロ点か100点の発想ではなく、自社で営業のノウハウを構築していけるようになさってください。
この記事の著者

経営・集客コンサルタント
平野 亮庵 (Hirano Ryoan)
国内でまだSEO対策やGoogleの認知度が低い時代から、検索エンジンマーケティング(SEM)に取り組む。SEO対策の実績はホームページ数が数百、SEOキーワード数なら万を超える。オリジナル理論として、2010年に「SEOコンテンツマーケティング」、2012年に「理念SEO」を発案。その後、マーケティングや営業・販売、経営コンサルティングなどの理論を取り入れ、Web集客のみならず、競合他社に負けない「集客の流れ」や「営業の仕組み」をつくる独自の戦略系コンサルティングを開発する。
